福井県を代表する観光地といえば、思い浮かぶのが断崖絶壁の東尋坊。
でも、そのすぐ近くに、まるで時間がゆっくりと流れているような静かな島があるのをご存じでしょうか。
それが「雄島(おしま)」
旅慣れた人ほど「東尋坊だけで帰るのはもったいない」と口をそろえる、知る人ぞ知る「神の島」。
観光地の喧噪からほんの数分離れるだけで、凪いだ海と古社の気配に包まれる。
そんな不思議な場所が、実は東尋坊のすぐ隣に。
今回は、雄島を楽しむための3つのポイントをご紹介します。
1.東尋坊から少し足を伸ばすだけ。福井の穴場スポットで心を洗う
東尋坊から車で数分。
朱色の長い橋が海の上へと伸び、その先にぽつりと浮かぶ島が見えてきます。
雄島と本土を結ぶのは、朱塗りの「雄島橋」。
ひとたびこの橋を渡り始めると、背後に日常がゆっくり遠ざかっていく。
潮風の音と波のリズムだけが耳に届いてくる。
途中でふと気づきます。
・・・音が消える。
まるで島が歓迎するかのように、静寂が自分の内側まで入り込んでくる不思議な感覚。
橋を渡り切ると、そこに現れるのは立派な鳥居。
ここから先は、自然と神域が重なる“別の世界”。
神隠しにでも遭うのではないかと、少し緊張しながら進みます。
森の中へ足を踏み入れると、湿った土の匂い、苔の深い緑、風が擦れる音。
観光地の「見る」体験ではなく、
五感でじっくり味わう場所が、雄島です。
島内は約30分ほどで周回できますが、急がず、ゆっくり。
ところどころに現れる奇岩・断崖・ゴツゴツとした荒々しい風景。
観光地化された場所とは違った味わいとして楽しむことができます。
2.源義経が奥州へ落ち延びる途中に立ち寄った「ゆかりの地」

雄島には、歴史ロマンをくすぐる逸話も残されています。
文治2年(1186年)、兄・頼朝に追われた源義経は、奥州・平泉へ向かう道中でこの地に立ち寄ったと伝わります。
義経は島内の安島神社を参拝し、家臣・亀井六郎の兜を奉納。
「一門の武運長久」と「海上安全」を祈願したとされています。
つまり雄島は、義経一行が最後の希望を抱きながら奥州へ向かった道程の一部。
彼らが見たであろう海、風、松林のざわめきを、今もそのまま感じることができます。
島の静けさの中を歩いていると、
ふと
「ここで義経はどのような思いで空を見上げたのか」
そんな想像が自然と湧いてきます。
3.「神の島」雄島。海の民が守り続けた信仰の場所
雄島には 安島明神(安島浦三保大明神) を祀る古社があり、
その歴史は白雉年間(650年代)にまで遡ると伝わります。
この神は、昔から海上守護の神として地元の漁師や船乗りに深く信仰されてきました。
かつてこの海域に外国船が侵入した際、
安島明神が霊験を示して退けたという伝承も残り、
文武天皇から3,700石もの社領が寄進されたという記録まであります。
古くは船乗りたちが航海前に必ず参拝し、
神前の矢羽を受けて海の安全を祈る風習もあったほど。
“海を知る人々が畏れ、敬い続けてきた島”
島全体が神域のような雰囲気をまとうのも、この歴史を知ると自然に感じられるはずです。
東尋坊だけで帰るのはもったいない。静けさと物語の島へ。
雄島は派手なスポットではありません。
大きな商業施設も、賑やかな売店もありません。
けれど、
橋を渡る時のあの“音が消える”感覚、
島に漂う淡い神気、
そして義経の物語を胸に歩く時間。
それらすべてが合わさって、
「あの島に行ってよかった」と、後からじんわり効いてくる旅の記憶になります。
東尋坊を訪れるなら、ぜひ雄島にも足を伸ばしてみてください。
その静けさは、旅のラストにそっと残る余韻になることでしょう。

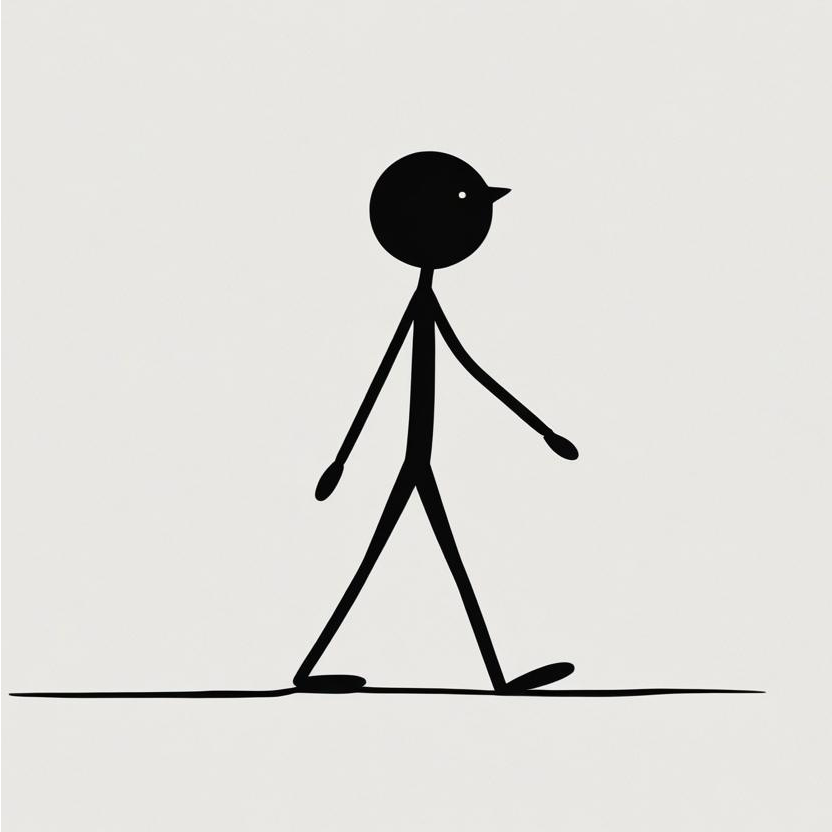 たびさんぽ
たびさんぽ


