「ラーメンショップ」
その、あまりにも直球すぎる屋号をどう捉えるかで、その人のラーメン遍歴が透けて見える気がする。
日本各地に点在し、どこかロードサイドの哀愁を漂わせるその赤い看板。
ネーミングの妙については評価が分かれるところだろうが、私は一周回って、確信に近い信頼を寄せている。
だって、看板に「うまい」って書いてあるんだもん。
その潔さは、もはや清々しい。
厨房という舞台、店主の舞
平日の昼どき。
横浜市瀬谷区にある「ラーメンショップ 二ツ橋」の前には、数人の男たちが静かに列を作っていた。
皆、それぞれの生活の合間を縫って、この一杯を求めて集まっている。
その事実だけで、期待は静かに膨らむ。
店内は、使い込まれた「くの字」のカウンター。
厨房を囲むその特等席に腰を下ろすと、客は皆、静かに大将の動きを見守ることになる。
湯気の中で麺が舞い、平ざるがリズミカルに音を立てる。
れはさながら、一杯のラーメンが完成するまでの「舞」を鑑賞しているかのようだ。
艶やかなラーメンと平日の昼下がりに
注文したのは、ネギチャーシューの普通盛り。
20代のころ、チャーシュー麺という響きはどこか遠い国の高級食のように感じられた。
あの頃の自分なら、ただの「ラーメン」で腹を膨らませるのが精一杯だった。
「まあ、今回は許してもらおう」 心の中で、誰に請いているのかもわからないような言い訳をしてみる。
30を過ぎ、多少の贅沢を自分に許せるようになった証左だろうか。
だが、着丼したそれを見て、わくわくにほんの少しだけ不安が混ざる。
ボリュームが、想定を超えていた。
肉肉しく、どこか「でろり」とした艶を放つチャーシュー。
誘ってきやがる。
なんともスケベな見た目に垂涎し、すぐにでも飛びつきたい衝動を抑え込み、何食わぬ顔で冷静を装ってみる。
濃厚な記憶と、変わっていく身体

スープを一口。 濃厚だが、決してくどくない。
動物系の旨みがガツンと鼻を抜け、気づけばレンゲを動かす手が止まらなくなる。
加水率低めの麺は、噛むほどに小麦の香りが主張し、スープの力強さに負けていない。
そしてチャーシュー。
しっかりと味が染み、噛み締めるたびに肉の意志を感じる。
「あぁこれ、白米がいるやつ」 脳が警報を鳴らす。
だが、同時に胃袋が悲鳴を上げる。
ここでご飯を投入すれば、私の腹は間違いなく破裂する。
かつては「中盛」を当たり前のように平らげていた。
が、今や、普通盛りを前にして、完食できるかどうかの瀬戸際に立たされている。
美味しいものを食べながら、ふと自分の「老い」を突きつけられる。
それは物悲しくもあり、どこか滑稽な自覚でもあった。
若さへの羨望、あるいは満足
満身創痍、とまでは言わないが、かなりの達成感とともに最後の一片を口に運ぶ。
なんとか食べ切った。
ふと隣を見ると、後から入ってきたカップルの女性が、私と同じネギチャーシューを涼しい顔で注文していた。
「若さってやつは……」 その健やかな食欲に、少しだけ嫉妬し、それ以上に好ましい。
店を出ると、外の空気は少しだけ冷たかった。
立派な見た目になった腹を抱え、重い足取りで歩き出す。
「次はライスも……」なんて無茶な思考がよぎるのは、きっとこの一杯に心から満足したからだろう。
看板に偽りなし。
やっぱり、ここは「うまい」。
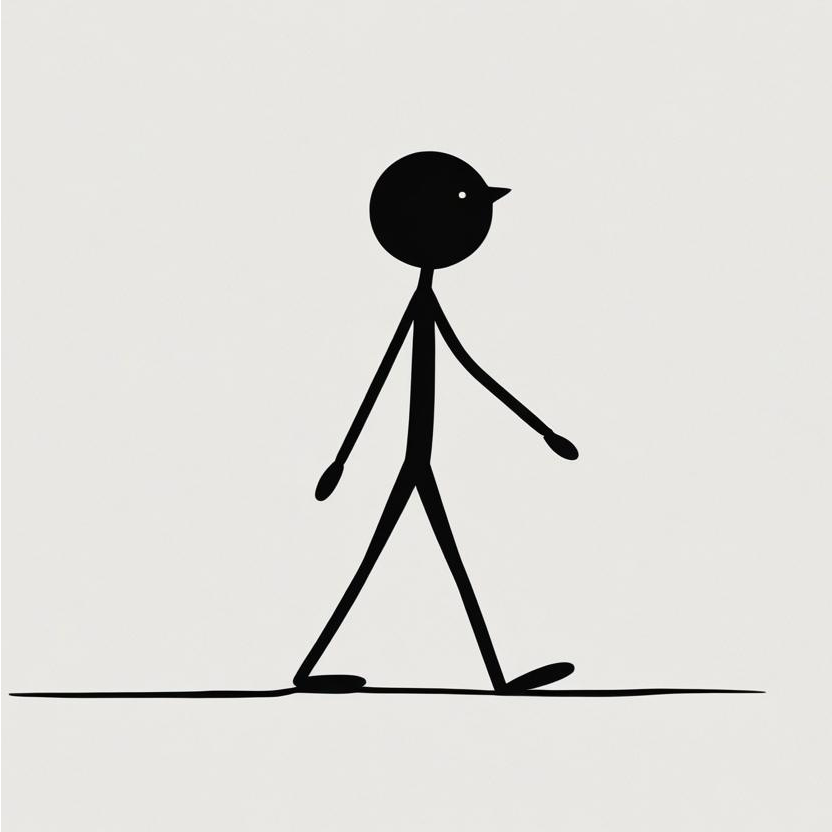 たびさんぽ
たびさんぽ


